「自分を知ってくれないことを気にかけないで、自分に才能がないことを気にかけることだ。」──承認欲求に効く論語の処方箋
SNSのいいね数が気になって夜眠れない。周りの人の評価ひとつで一喜一憂する。現代では「承認欲求」に悩む人が増えています。そんなあなたに、孔子の言葉がぐっと刺さります。
💡 今日の一節
人(ひと)の己(おの)れを知(し)らざることを患(うれ)えず、己れの能(のう)なきを患う。(人が自分を知ってくれないことを気にかけないで、自分に才能がないことを気にかけることだ。)※憲問第十四(三二)より一部抜粋
孔子はこう言っています。「他人が自分を理解してくれないことを悩むな。まず、自分にできることが足りないのではないかと考えよ」──つまり、外の評価に翻弄される前に、自分の中身(スキルや実績)を強くしていこう、ということです。
承認欲求は“自然”なこと。問題は依存すること。
まず断っておくと、承認欲求そのものは悪ではありません。人は誰かに認められたい生き物ですし、承認はモチベーションになります。問題になるのは「承認に依存してしまう」状態です。例えば、
- 投稿の「いいね」で気分が決まる
- 評価が下がると自己肯定感も急落する
- 他人の顔色をうかがって行動がブレる
こんなときこそ、孔子の一言を思い出しましょう。「人の己を知らざることを患えず」──他人に知られていないことを嘆くより、「自分が本当にできているか」を見直すことが大切、というわけです。
「知られたい」を「できるようになりたい」に変えるテクニック
ここからは実践編。承認欲求を健全な推進力に変えるための方法を、すぐ使える形で紹介します。
- 基準ノートを作る
「自分が評価されたい基準」を3つ書き出す(例:丁寧さ/期限厳守/学び続ける姿勢)。外からの評価が来たら、この基準に照らして受け取る。 - アウトプット最小実験
学んだことは24時間以内に1つだけ試す。成功/失敗をメモして「できる」を貯金する。 - フィードバックの分散化
一定の評価だけでなく、同僚・家族・友人・顧客・自分の振り返りを合わせて評価のバランスをとる。 - 「何のために発信するか」を決める
SNS投稿の目的を「承認」ではなく「記録」「学びの共有」「誰かの役に立つ」などに設定する。 - 週1の「できたリスト」
週に1回、3つの「自分ができるようになったこと」を書く。自己信頼はこうして育ちます。
ストーリー:承認欲求を“燃料”にした人の例
あるライターAさんは、毎回いいねの数で一喜一憂していました。そこで方針転換。「1ヶ月で3つ、新しい技術を試して記事にする」と自分ルールを決め、いいねは二の次に。結果、スキルが上がり、読者の質も変わり、やがて自然な反応が増えました。外の評価に頼るより、自分を磨く方が長期的に満たされるのです。
まとめ:孔子が現代にくれた処方箋
孔子は私たちに静かに告げます。「人に知られないことを悩む暇があったら、自分の力を磨きなさい」と。承認欲求を完全に消す必要はない。むしろ、それを自分の成長に向けることで、外からの評価は副産物としてついてくる──そんな視点が、健やかな自己成長へと導いてくれるのかもしれません。
あなたが、あなたの「論語」を見つけるきっかけになりますように。
(よければこの記事をSNSでシェアしてください。あなたの「承認欲求」をうまく活かすコツがあれば、ぜひコメントで教えてください。)
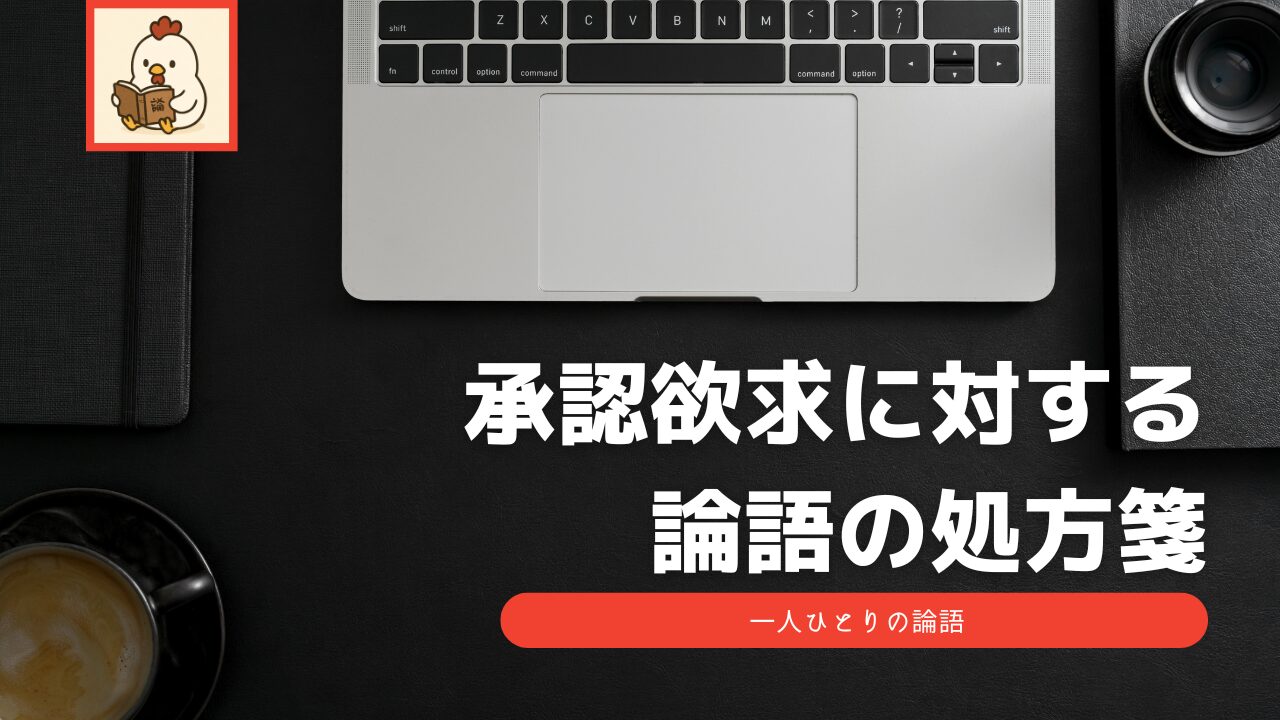


コメント