※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
こんにちは、へむきーです。
論語は、2,000年以上読み継がれる「知恵」。これまで延べ3,000人以上に、論語をもとにした学びや実践のヒントを伝えてきました。

うちの子、どうして学校に行けなくなったんだろう…。どう対応すればよいのかわからない…。

焦る気持ちや心配する気持ちは、子どもを思うからこそ。でもその思いが強すぎて、つい“子どもに変わってほしい”という方向に向かってしまうこともあります。
焦って言葉をかければかけるほど、子どもは心を閉ざしてしまう。

私の接し方が悪いのかな…。

そんな優しいお母さんに、今日は伝えたい言葉があります。
この記事では、不登校の高校生に悩む親御さんへ向けて、子どもの心を理解するためのヒントと、実際に解決してくれる【キズキ共育塾】という選択肢を解説します。
この記事を読むことでわかること
・まずは、焦りや不安を少し手放して「子どもの気持ちを理解する」ことから始める。
・家庭だけで抱え込まずに、相談できる場所をもつことは重要。安心して学びを再スタートできるサポートとして「キズキ共育塾」の無料面談を利用することが、早く解決に導く。
・子どもへの接し方に“安心と方向性”が見えてくる

大丈夫!行動を起こせば、必ずよい方向に進みます。
【2025年最新】キズキ共育塾の料金と口コミまとめ|不登校の子に本当に合う塾なのか?
Q:不登校の高校生にどう接すればいい?A:“親子関係”がカギ
◆結論:「理解しようとする姿勢」が、子どもの一歩を生む
子どもが学校に行けないとき、親として最初にできることは「励ますこと」ではなく、「理解しようとすること」です。

「己(お)のれの欲(ほっ)せざる所(ところ)、人(ひと)に施(ほどこ)すことな勿(な)かれ。」¹)
もし自分が落ち込んでいるときに「頑張れ」と言われたら、少しつらい気持ちになるかもしれません。

子どもも、今は「動けない自分」を責めている最中。そんなときこそ、理解の姿勢が回復のカギになるのです。

私ばっかりが焦って、全然子どもの気持ちを理解しようとしてなかったかも…。
親が理解を示すと、子どもは安心し心を開き始める

子どもが不登校になる背景には、友人関係、先生とのトラブル、自己否定感など、さまざまな要因があります。
しかし共通しているのは、「自分は理解されていない」という孤独感です。
反対に、「つらいね」「無理しなくていいよ」「いつでも話せるからね」と、まずは気持ちを受け止めてあげるだけで、子どもの表情が少しやわらぐことも。
心理学的にも、“共感されること”が人の自己肯定感を回復させる最初のステップだと証明されています。
親が変わったら、子どもが動き出した
私の姉は、息子が高校1年のときに不登校になりました。 朝起こしても無言、食事もほとんど口にせず、部屋に閉じこもる日々。

どうして行かないの?将来どうするの!?
問い詰めてばかりでした。
ある日、心理カウンセラーの先生に、

お母さん、まず“この子がどう感じているのか”を聴いてあげて
と言われ、はっとしました。その日から、「どうしたの?」ではなく、

今、どんな気持ち?
と声をかけるようにしたんです。すると、少しずつですが息子が話してくれるようになり、ある日突然「また勉強してみようかな…。」と言いました。
彼が最初に通い始めたのが【キズキ共育塾】今では少しずつ外出の時間も増え、「自分のペースで頑張ってみたい」と前向きな言葉が出てきています。
子どもの心を支える「第三の場所」を見つけよう
親の理解は、子どもにとって最初の支えですが、すべてを家庭で抱え込む必要はありません。
【キズキ共育塾】
![]() のように、不登校や発達特性に理解のある専門家がサポートしてくれる環境を活用することも重要です。
のように、不登校や発達特性に理解のある専門家がサポートしてくれる環境を活用することも重要です。

子どもにとって、学校でも家でもない「安心できる第三の場所」を持つことが、回復の大きな一歩になります。
◆行動を支える3つの具体策
- ①「聴く」時間を作る:毎日数分でも、子どもの言葉を遮らず耳を傾ける。
- ②「責めない」姿勢を持つ:行動よりも、気持ちを理解しようとする姿勢を大切に。
- ③「専門サポート」を頼る:家庭だけで抱えず、キズキ共育塾など専門家に相談する。
まとめ
・まずは、焦りや不安を少し手放し「子どもの気持ちを理解する」ことがすべての出発点。
・家庭外でも安心して学べる居場所「キズキ共育塾」の無料面談を利用することで、子どもは“もう一度学ぶ喜び”を取り戻すことができる。
・子どもへの接し方に“安心と方向性”が見えた。

あなたの「理解しようとする一歩」が、子どもの未来を変えていくのです。
最後まで読んでくれてありがとう!
おすすめ・参考書籍
¹)金谷治訳注『論語』岩波文庫 衛靈公第十五(二四)より一部抜粋
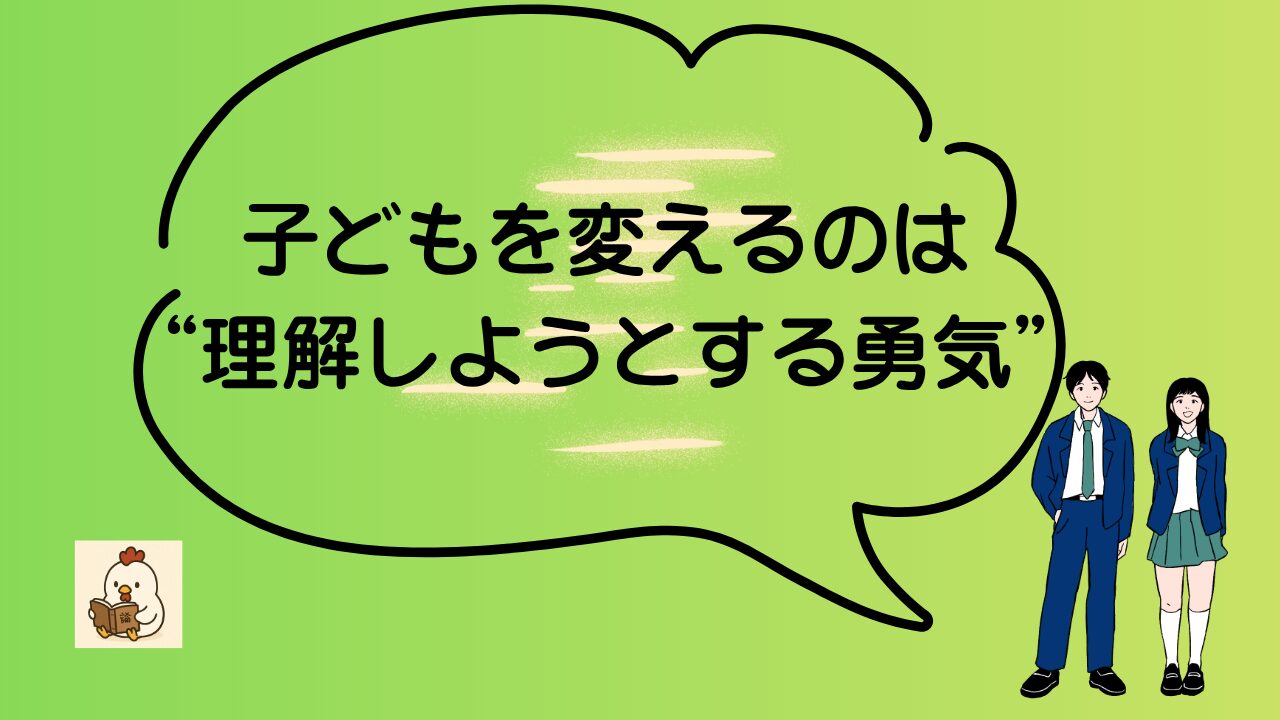
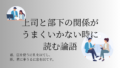
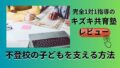
コメント