「旧悪を念わず」──過去を水に流せたら、人はもっと自由になれる
誰かに嫌なことをされた。
言い返せなかった。
許せないまま、時間だけが過ぎていった。
そんな心の「しこり」が、あなたの中にもありませんか?
孔子が尊敬してやまなかった、古代の兄弟「伯夷(はくい)と叔斉(しゅくせい)」には、
学ぶべき美徳がありました。
🌿 今日の一節
子曰(し、のたま)わく、
伯夷(はくい)・叔齊(しゅくせい)、旧悪(きゅうあく)を念(おも)わず。怨(うら)み是(ここ)を用(もっ)て希(まれ)なり。 (先生がおっしゃった、「伯夷・叔齊は、[清廉で悪事を憎んだが]古い悪事をいつまでも心に留めなかった。だから怨まれることも少なかった」)※公冶長第五(二三)より抜粋。
過去を引きずらないという、美徳
伯夷と叔斉は、古代中国の兄弟です。
父王の跡継ぎをめぐって対立したり、
戦乱や不正義の世の中に心を痛めたりしながらも、
一貫して「清廉潔白」に生き抜いた人物として知られています。
その中でも、孔子が特に感服したのがこの部分。
「彼らは、過去の悪事や恨みを心に留めなかった」
だから、心に「怨み」が生まれることがとても少なかったのだと。
なぜ、私たちは「旧悪」を忘れられないのか
実際、現代の私たちはどうでしょうか。
- あのとき言われた一言が、今も頭から離れない
- 理不尽な扱いをされた記憶が、ずっと心に残っている
- 「許した」と思っても、ふとした瞬間に怒りがよみがえる
それは、決して「心が狭いから」ではありません。
私たちには、「傷ついた記憶を繰り返し思い出す」習性があるのです。
恨みを手放すことは、自分を自由にすること
でも、伯夷と叔斉は、それを「思い出さない」選択をしました。
相手の過去を許したのではなく、
それに縛られる“自分の未来”を許したのかもしれません。
怨みを抱き続けることは、
過去の相手に、今の自分の心を支配させてしまうこと。
逆に、忘れること・水に流すことは、
自分の人生の舵を、自分の手に取り戻すことだとも言えます。
「自分の感情に責任をもつ」という勇気を
旧悪を「思い出さない」と決めることは、
「自分の感情に責任を持つ」という覚悟。
もちろん簡単ではありません。
でも、伯夷と叔斉がそうであったように、
「恨みを手放した人」には、静かで大きな人間力が宿ります。
🪶 あとがき
過去は変えられない。
でも、それを「どう抱えるか」は、自分で選べる。
心の中にある「古い怨み」──
もしかしたら、もう手放してもいいのかもしれません。
あなたが、あなたの「論語」を見つけるきっかけになりますように。
ないものはない!お買い物なら楽天市場


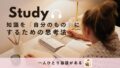
コメント